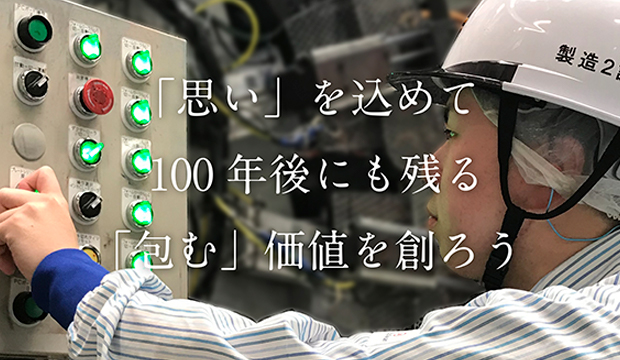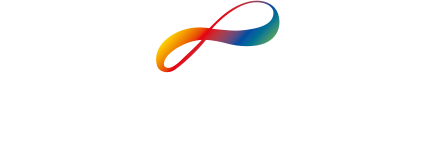Technology技術情報
ダイヤカット缶
1.ダイヤカット缶の開発意図と経緯
破壊から創造へ~ダイヤカット缶の源流
ダイヤカット缶の源流は、1960年代後半に三浦公亮先生が研究されていた「PCCPシェルコンセプト」に遡ります。当時、NASAの研究所で超音速機の胴体の破壊について研究していた三浦先生は、いろいろな筒状の胴体の破壊の形を見いだし、そこに見られる美しい幾何学的パターンに魅了されていました。
ある時、その破壊モデルが、ある種の外力に対しては、破壊していないものよりもはるかに強いことに気づき、「始めから破壊した形を作れば、新しい構造ができる」という構想に到達しました。こうして、ダイヤカット缶の元となった「PCCPシェル」のコンセプトは、文字通り「破壊」から創造されていったのです。
コンセプトへの着目~缶の軽量化

1980年代の始め、東洋製罐グループの基礎研究部門「綜合研究所」の研究員が、当時軽量化対策の主流であった「ベローズ形状(横ビード)」に変わる缶の形状パターンとして前述の「PCCPシェル」に注目していました。試作品を作り強度を測定したところ、パネリング強度(※)が通常の3倍もある上に、ベローズ形状とは違い、縦方向の加重に対しても充分な強度があることがわかりました。優美なフォルムの中に、缶を軽量・薄肉化する鍵が隠されていたのです。
※パネリング強度 筒の内側へのへこみに耐える強度のこと。側壁の板厚によって変化する。
TULCとの融合

生産システムの開発が始まり、当初は前述の3ピース缶で開発しようとしましたが、
円筒接合部の品質を保つのが難しく、2年後に一端断念しています。
その後普及を始めた「胴体につなぎ目の無い2ピース陰圧缶」であるTULCの出現によりPCCPシェルの実用化が現実のものとなりました。
PCCPシェルコンセプトへの着目以来、幾年もの時を経て、第一号の生産機が毎分1500缶のスピードで製缶を開始した時の感慨は、云うに尽くせないものでした。こうしてPCCPシェルのコンセプトはTULCという技術のうえに結実したのです。
2.ダイヤカット缶の製品特徴
スチール製ダイヤカット缶の特徴

パネリング強度の向上
材料の厚みが同じ「ストレート缶」と「ダイヤカット缶」の空缶にふたをして、水に沈め水圧に対してどの程度の強度を保つか、比較試験の結果があります。
加工の無いストレートの缶は水深8mあたりでへこみ始め、15mで完全にペシャンコになります。一方、PCCPシェル加工を施したダイヤカット缶は、15mでも全く変化せず、水深30mになってようやくへこみます。この結果でもわかるとおり、ダイヤカット缶のパネリング強度は、ストレート缶の3倍にも達します。
※パネリング強度 筒の内側へのへこみに耐える強度のこと。側壁の板厚によって変化する。
30%(※)軽量化
環境配慮や製造コストを抑えるという面から、「材料をいかに減らすか」という問題は容器包装にとって永遠の課題となっています。前述どおり、パネリング強度が大きいと云うことは、それだけ缶の板厚を薄くしても大丈夫ということになり、材料を節減できることになります。加工により強度を増したダイヤカット缶の重量は、従来の缶より30%も軽くしても同じ性能を保つことができ、大幅な軽量化を実現しました。
※自社製品比
特徴的なデザイン
直線の構成により円筒に近い形を求め、数理的に導き出されたPCCPシェルのフォルムは、合理性の導き出したフォルムといえるでしょう。その合理性は不思議なことに彫刻作品のような気品ある美しささえも生み出しています。偶然ではありますが、このフォルムは手に持った時に滑りにくく、非常に持ちやすいという特長も生み出しました。
また、印刷デザイン面でも、その抽象的な形状が、従来のストレート缶では表現できなかった奥行きや立体感のある新しいパッケージデザインを導き出し、店頭での陳列効果にも大きなプラスとなっているのはみなさんご周知の通りです。
アルミ製ダイヤカット缶の特徴

アクション
缶を開けたときに、音とともにダイヤカット形状が現れ、消費者にサプライズを与えます。開缶前は内容物の炭酸ガスが缶の内壁を押す働きをし、ダイヤカットは目立たない状態となっていますが、開缶後に炭酸ガスが抜けることで、加工された形状が浮きあがります。
また、アルミの素材感から光の反射によるキラキラ感があり、製品の冷涼感を効果的にあらわす働きもしています。